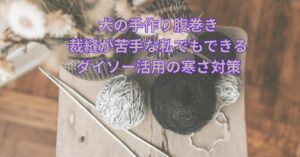老犬の夜の介護がつらいときに。眠れない夜を少しでも穏やかに過ごす工夫
老犬の介護でいちばん心が揺れるのは、夜かもしれません。
静まり返った部屋の中で、愛犬の動く音や呼吸が気になって、眠れないまま朝を迎えることもあります。
けんしも、そんな夜を何度か過ごしてきました。
介護の始まりで戸惑うときは、老犬介護の始め方|無理せず、今日できる準備から も読んでみてください。
夜になると老犬が落ち着かなくなる理由
老犬になると、昼夜の感覚が少しずつ変わってきます。
かかりつけの獣医によると「老人性の昼夜逆転」といわれるもので
昼によく眠り、夜になると活動的になることがあるそうです。
けんしも、朝の散歩を終えると、夕方まではほとんど寝ています。
夕食を食べたあとは比較的起きていて
家族の食事の時間に一緒にいたり、ふらふら歩いたりしています。
普段は夜9時頃に寝て、朝までぐっすり眠るのですが
夏場の暑い時期には、夜中に起き出してはしゃぐこともありました。
その姿を見ると、「元気がある」と安心する気持ちと
「この時間に動くの?」という小さな戸惑いが同時にやってきます。
老犬の夜の行動は、体のリズムの変化とともに起きる自然なこと。
少しずつ、その新しい夜のかたちを受け入れるようになりました。
夜の介護を少しでも楽にする工夫
夜中に動くことが増えたら、まず環境を整えることから始めました。
・暗すぎると不安が強くなるので、常夜灯をひとつ灯す
・フローリングには滑り止めマットを敷く
・寝る位置を家族の気配が感じられる場所にする
たったそれだけでも、けんしの落ち着きが少し変わりました。
夜中にふらっと立ち上がっても、危なくないように通路を広めにしておく。
「何かあっても大丈夫」という環境があるだけで、私自身の安心感も違います。
そしてもうひとつ、私が夜に欠かさずしている準備があります。
もし夜中に急に体調を崩しても、すぐに動けるようにしておくことです。
ベッドの脇には、すぐに着替えられる服(ブラトップや部屋着など)を置いています。
その横には、けんしの診察券や保険証、財布、鍵をひとまとめにした小さなカバンも。
夜中の不安な時間帯に「探さなくても、すぐに対応できる」というだけで、心が少し落ち着きます。
こうした小さな準備が、「いざという時に慌てない夜」をつくってくれます。
老犬介護は、安心の積み重ねが、心の余裕につながると感じています。
体調の変化が気になるときは、食事と体調管理|シニア犬に合う暮らしの整え方 も参考になります。
眠れない夜が続いたあの頃
今でこそ落ち着いていますが、膵炎で入院する前のけんしは
夜中や明け方に吐くことが多く、毎晩のように気配を感じて目が覚めていました。
吐く前の動きや呼吸の変化がわかるほど、神経が張りつめていた時期です。
眠りについても、けんしが動く音ひとつで目が覚め、少しの咳にも体が反応してしまう。
原因不明の腹痛で入院した夜は、心配でほとんど眠れず、明け方に救急へ連れて行きました。
あの夜の空気は、いまでも覚えています。
不安で押しつぶされそうだったけれど、「助けたい」という思いだけで体が動いていた気がします。
今の夜と、心の整え方

今のけんしは比較的穏やかで、夜中に起きることも減りました。
私もようやく、眠りながら見守れるようになりました。
それでも、咳をしたり体を動かす音が聞こえると、反射的に目が覚めてしまいます。
「眠れない自分」を責めることもあったけれど、今はそれも含めて、介護の時間なんだと思うようにしています。
夜は、介護をしている人にとって孤独を感じやすい時間。
けれど、その静けさの中にある呼吸の音、あたたかな毛の感触は、確かに生きているという証です。
完璧でなくていい。
お互いが少しでも安心できる夜を過ごせるように、今日も灯りをひとつつけて、そっと寄り添います。
介護と仕事の両立に悩んだときは、老犬の介護で仕事を休むべきか迷ったら の体験記もどうぞ。